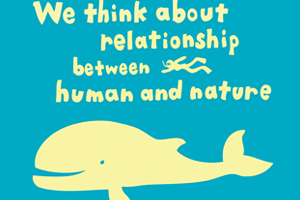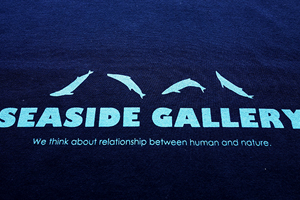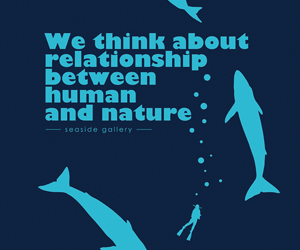夏休みの特別企画!太平洋をまるごと堪能しよう!
ホエールウォッチング&漁港で味わう海鮮BBQツアー
日時 :2015年7月25日(土)・26日(日)、8月8日(土)・9日(日)の計4回
場所 :入野漁港(高知県幡多郡黒潮町入野227-ロ)
スケジュール :9時~13時 ホエールウォッチング(8時半集合)、13時~ 海鮮BBQ
料金 :大人9,800円、小学生5,500円、幼児1,000円(税込)
自然のクジラに会いにいこう!

↑水族館では決して体験できない迫力満点のホエールウォッチング
360度が水平線、地球!を感じられる広い太平洋で、悠々気ままに出迎えてくれるニタリクジラは、そのスラリとした優美な体付きと、あまり警戒しない穏やかな性格から、「海の貴婦人」とも呼ばれるとても美しいクジラです。
大方ホエールウォッチングの特徴は、何と言っても漁師さんの漁船に乗っていくところ。海を知り尽くした船長が、あなたの4時間の旅をエスコートします。キラキラ光る海、潮の香り、吹き渡る風、自然を体いっぱいに感じながら大海原を突き進み、ニタリクジラに会いに行きましょう!
大方ホエールウォッチングの詳しい情報は、コラム『人と動物、長いつきあいを目指して:大方ホエールウォッチング』をどうぞ!
漁港で味わう海鮮バーベキュー!

ホエールウォッチングを十分に堪能したら、今度は漁師さんが獲った魚介類で豪快に海鮮バーベキューを味わいます。しかも、大方ホエールウォッチングの海鮮バーベキューは、船長が漁師さんだけあって、水揚げした漁港でそのままバーベキューをしちゃいます!普段では体験できることのないいつもと違った雰囲気が気分を一層盛り立ててくれますよ♪
当日の漁の状況によって食材が変わるので、何が出てくるかは当日のお楽しみ!
お申込み・お問い合わせ
ご予約はご希望日の7日前までにお申し込みください。
また、このツアーにおきましては、最少催行人数が大人6名からとなっておりますので、人数が大人6名に満たない場合は中止となりますのでご了承ください。※中止のご連絡は、5日前にいたします。
①お電話 0880-43-1058(大方ホエールウォッチング事務局、8:30~17:00)
②ホームページ 大方ホエールウォッチング・ツアー申込ページからどうぞ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
大方ホエールウォッチング(おおがたほえーるうぉっちんぐ)
黒潮町にある大方遊漁船主会が運営。今年で26年目となる。
大方ホエールウォッチングの詳しい情報は、コラム『人と動物、長いつきあいを目指して:大方ホエールウォッチング』をどうぞ。ホエールウォッチングのご予約はこちらから。