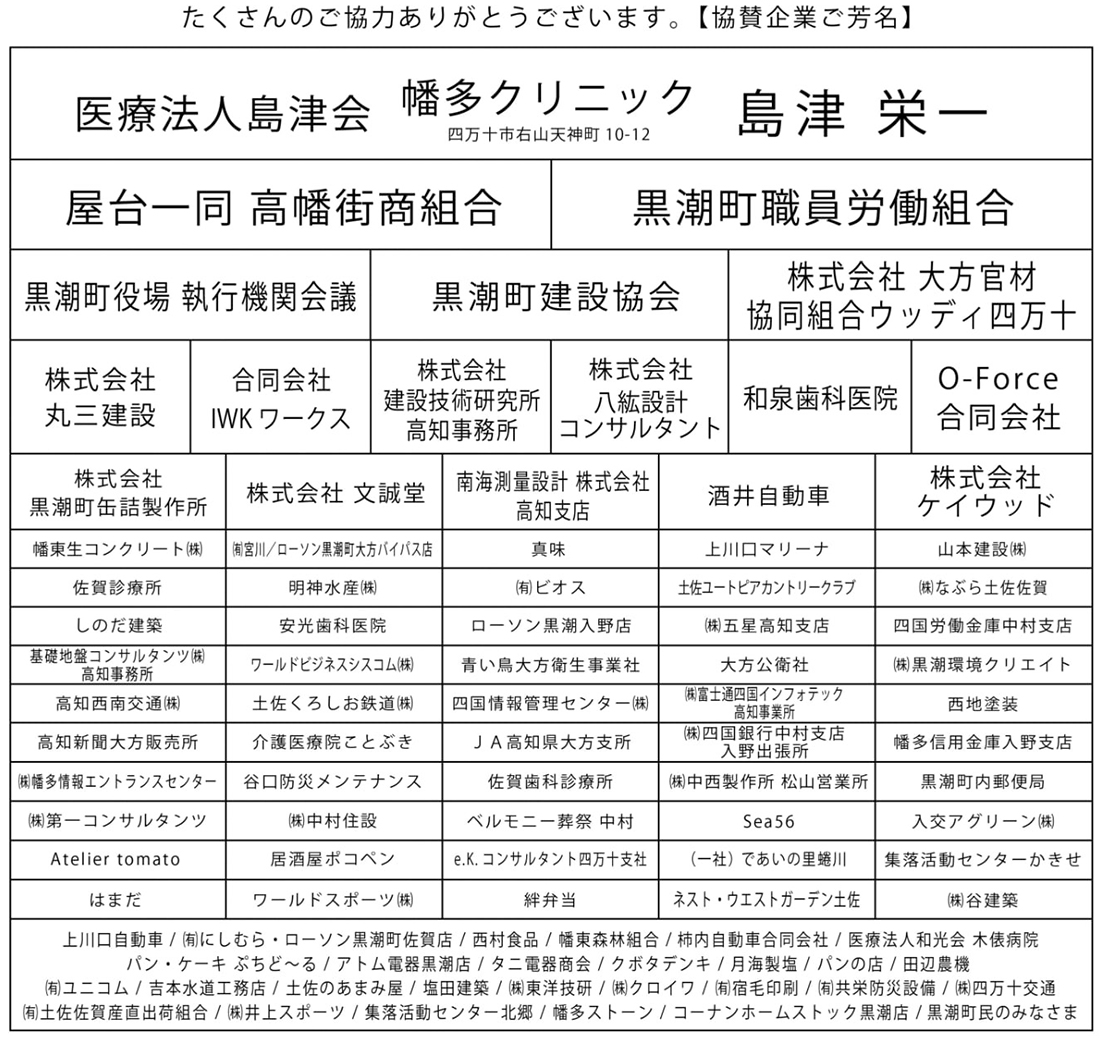砂浜美術館のある町、黒潮町には数年前より「空想をカタチにする町」というキャッチコピーがある。このコピーにはある仕掛けがあり、空想と書いて【モウソウ】というルビが充てられている。妄想癖のある私としてはとても好きなコピーである。ある日、いつものように砂浜の入り口にあるベンチに座ってこの空想という文字に自分がルビを充てるならどうするだろうか考えたことがあった。このベンチは砂浜と松原の間あり、普段はサーファー達が海を眺めながら良い波が来るのを待っている。私が砂浜美術館の企画を考える時はほとんどがココであり、私にとっての「カンガエルバ」である。少し話が逸れてしまったが、【空想】という文字に自分がルビを充てるなら……。【かのうせい】が頭に浮かんだ。私は可能性がゼロでない限り、一度はアプローチしたい性分である。そして私にとっては「可能性」=「砂浜美術館」なので変わったことをしているつもりはない。現実的ではない「可能性」を優先してしまう癖について自分なりに考えてみた。おそらくこれは「オモロい」がベースにあるのだろう。砂浜で授業するから「すなはま教室」。砂浜に町長が出勤してくるから「すなはま町長室」。それなら環境大臣が来るなら……オモロそうだな。ということで昨年は「すなはま環境大臣室」を創った。大臣が霞が関の自室からネームプレートを持ってきたことは予想外のオモロさだった。すべて「砂浜でこんなことができたらオモロいだろうな」という発想から動き出したことだ。

砂浜に流れ着くゴミも、大切な【かのうせい】である。砂浜には毎日たくさんの作品(漂着物)が無償で届く。当然招かざる作品も届くわけだが、私が特に好きなのは「メッセージボトル」である。この「メッセージボトル」を起点に、これを流した本人に会いに行くという企画が立ち上がり、2023年にアメリカへ渡った。差出人に会いに行く途中にヒューストンという街があり、そこにはNASA(アメリカ航空宇宙局)があった。先に書いた私の性分からその後の行動を想像して頂きたい。結果としてNASAに入館し、興奮そのままに、後日NASAの現役職員が黒潮町を訪れ、子ども達に夢や宇宙の話をしてくれるという尾ヒレまで付いた。砂浜に勝手に届いた作品がNASAへと繋がるのだから砂浜美術館はオモロい。どの企画もきっかけは単純に自分がオモシロがりたいだけ。そう考えると【空想】に充てるルビは「オモロい」になるのか。ここからは私のまだやっていないが「オモロそう」を紹介したいと思う。
ルーブル美術館で漂流物展
砂浜に流れ着くゴミを並べて楽しむ「漂流物展」と、ひとつの漂流物を題材に、流れてきたワケを自分勝手に想像した物語を公募する「漂流紀行文学賞」という企画を行っている。この作品展を海外の人向けに開催したらオモロいのではないだろうか?漂流物は環境・文化・歴史・科学などの様々なインスピレーションを与えてくれる。「パリのルーブル美術館で漂流物展」海外の美術館といえばでルーブルしか出てこないあたりが自分らしい。【漂流物展 in Musée du Louvre】みなさまぜひ会場に足を運んで頂きたい。
修学旅行はNASA
アメリカ航空宇宙局。そこは宇宙を軸に、航空力学・海洋学・農業・環境・医療・文化や歴史に至るまで様々な研究が行われている機関で、言い換えれば可能性の宝庫なのである。私の中では【NASA=可能性=砂浜美術館】になるので、そんな場所を町の子ども達が訪れ、NASAのスタッフに方言で質問を投げかける。きっとそこにはオモロい風景が広がっているに違いない。「黒潮町の子どもたちは修学旅行でNASAに行っています。」食いつく人は多いのではないだろうか。
カリフォルニアでひらひら
砂浜美術館の前の海の少し向こうにカリフォルニアビーチがある。ムキムキマッチョのお兄さんや、金髪のビキニのお姉さんが沢山いるビーチでTシャツが風に揺れる風景は、Tシャツたちもいつもより陽気にひらひらとはためくに違いない!
入野松原特別名勝指定に
砂浜美術館のすぐそばにある入野松原は、2028年2月に国の名勝指定100年を迎えます。(名勝:すぐれた国土美の有様を様々なかたちで表現するもの)
砂浜美術館でも30年前から秋に「潮風のキルト展」をこの松原で開催し、隣接するラッキョウ畑にはピンクの花が咲きほこり松原に季節の彩りを加える。この町の学校遠足では、昔からこの松原を通って砂浜へ行くのが定番で今もなお続いている。松原は町民にとっては思い出の場所であり、砂浜美術館にとっても地域文化の溶け込んだ一大作品でもある。そんな入野松原が「国の特別名勝(特別名勝:名勝や史跡のなかで、特に学術的価値が高く、日本文化の象徴ともいえるもの。)に指定!」当たり前にあった松原の価値観が突然変化する。これはこれでオモロそう。

色々書いたが、結局「オモロいをカタチにする美術館」私にとってはそれが砂浜美術館である。今回書いた妄想はすべて実行する予定だ。ただ、開催時期が未定なだけ。ひとまず開催時期がくるまでは、いつものベンチに座り、海をみながらオモロいことを妄想しようと思う。そして良い波が来た時に、直ぐに駆けだせるサーファーのように準備だけはしておこう。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

松下 卓也(まつした たくや)
黒潮町海辺生まれ。
砂浜美術館映像部でケーブルテレビ等を担当。
企画チームリーダーとして事業部をまたいだ活動も担当している。