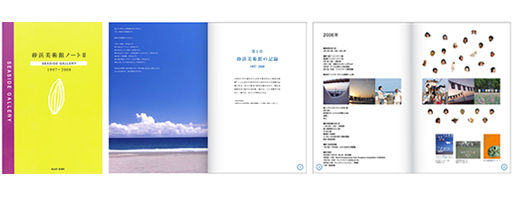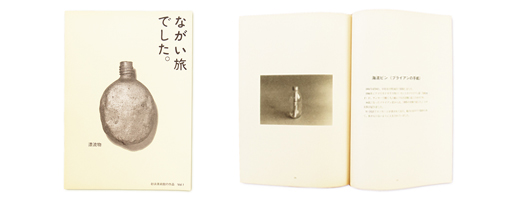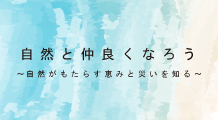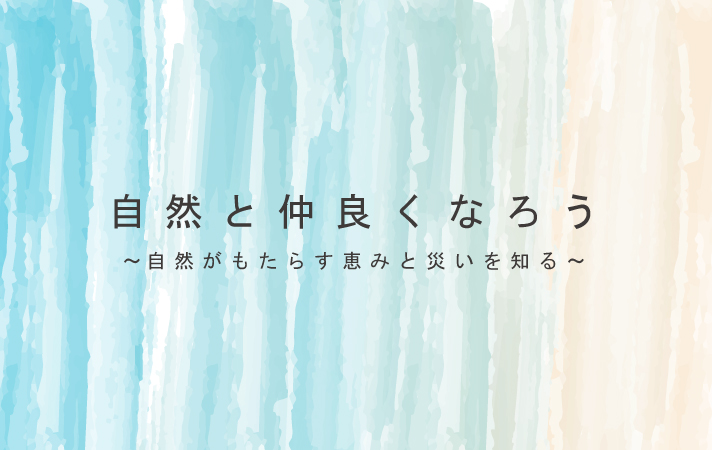↑沖にはニタリクジラが棲んでいる
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
<前口上>
このインタビューについて
インタビューは1997年2月8日から10日にかけて、大方町の砂浜美術館事務局、入野の浜、魚市場、黒砂糖工場、居酒屋、うどん屋、佐賀町の天日塩工場を会場に行った。
また、参加者が14人と多いため、砂浜美術館の関係者の発言をまとめて”細字”とした。”太字“はインタビュアーの発言であり、中川理(京都工業繊維大学助教授)と花田佳明(建築家、神戸山手女子短期大学助教授)が務めた。
※このインタビューは、1997年に発行した『砂浜美術館ノート』(非売品)からの転用です。地名や肩書きなどは当時のまま修正せずに使用しています。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
結局、砂浜美術館はあるとき突然できたものではなくて、
大方町に元からあった地域文化が、砂浜美術館というかたちになって立ち上がっただけではないかとぼくは考えています。
大方町に来て、みなさんと話していてわかるのは、おおらかというか、いい意味でのアバウトさですね。いまはどこの町村でも余裕が感じられませんが、余裕がないところからは砂浜美術館的な発想は出ようがない。
そんなことはなくて大方町も深刻なんです(笑)。でも、深刻ぶったところで問題の解決にはつながらないですから。
見ていて無理を感じないんですよ。自然体でいられるということは、思想があるからだと思います。しかし、それがどういう思想なんだとたずねられても説明しづらいかもしれませんが。
じつは、当のぼくたちも気づいていないことが多いんです。
思想とは別の方向で説明すると、前史がしっかりしていたんだと思います。結局、砂浜美術館はあるとき突然できたものではなくて、大方町に元からあった地域文化が、砂浜美術館というかたちになって立ち上がっただけではないかとぼくは考えています。
砂浜美術館という考え方も、ぼくたちがつくろうとしてできたものではありません。偶然の人と人の出会いがきっかけで、そうした出会いを楽しみにながら、さらに出会った者同士がもっと楽しくなるために動いた結果こうなったのですから。
いま、偶然といわれたけど、かなり必然な出会いだったと思います。だからこそうまくやってこられたのではないでしょうか。そう考えると、松本さんと畦地さんがデザイナーの梅原さんにはじめて出会った1989年5月20日という日は、きっとあらかじめ歴史に設定された時限爆弾だったのですよ。ところで、最初の話に戻りますが、砂浜美術館のものの見方や考え方を伝えていく上でたいへんなことはどんなことですか。
Tシャツアート展などの展示会も考え方を伝えるために行ってきたわけですが、やはりどこかでイベントと一緒にされてしまいます。一度、町の議員から「Tシャツ美術館」とまちがわれたこともありました。また、「次の砂浜美術館はいつですか」という問い合わせが、いまでも事務局に入ります。ぼくたちの力不足もありますが、砂浜美術館は考え方なんだといくら説明しても、まだまだイベントとしてしか理解されていないのですね。
理解されないといえば、Tシャツアート展はある意味で今日的な環境アートなのだけど、少し前まではシーサイドギャラリー・夏の中で盆踊りと一緒に開かれていました。違和感があるというか、砂浜美術館のコンセプトと照らし合わせてどうなんだろうと思います。
盆踊りは町からの補助事業だから、分けられなかったという経緯もありますが。
それは考え方さえできてしまえば、あとは、何があってもいいやと受け入れる余裕が生まれたのかもしれませんね。
盆踊りも作品と考えましょう(笑)。
それで「もうやめようぜ」となったわけです。
高知新聞に「イベントは今回限り」とコメントを載せて、
1994年をさいごに夏のシーサイドギャラリーのような大規模なイベントは中止しました。
だけど、ぼくたちはイベントそのものを否定しているわけではありません。でもイベントをすることが目的になっては、やはりだめなのだと思います。イベントは、所詮、数の論理です。予算はいくらか、お客さんは何人来たか。それに毎年のように内容のレベルアップが必要。去年と同じレベルを維持したつもりでも、お客さんはそうは見てくれない。去年と同じなら「レベルが落ちた」といわれる。
数や規模を追うときりがありません。
砂浜美術館も、1994年までは展示会の数や規模が、年々、過剰になっていったんです。お金も労力もかなりかけました。当時は、実行委員会の中に総務部をはじめ、砂像部、自然部といった部があったくらいですから。砂像部長だった武政登さんは、早朝、出勤前に砂浜で砂像を彫って、仕事の途中で抜け出してまた彫って、仕事が終わってさらに彫って・・・。それでも間に合わないんです。
やりたいからやっているではなく、そうなるとやらなくてはいけないという悪しき状態ですね。
それで「もうやめようぜ」となったわけです。高知新聞に「イベントは今回限り」とコメントを載せて、1994年をさいごに夏のシーサイドギャラリーのような大規模なイベントは中止しました。砂の彫刻展は中止し、Tシャツアート展は5月の連休期間にずらしました。ここでぼくたちがいいたかったのは、今後は、大勢の人を集めることを目的とするイベント的な開催はせず、砂浜美術館の考え方を伝えるための企画の展開を図っていきたいということです。
思いきりよくやめられたのも、考え方があったからですね。
そうですね。考え方がなかったら全部やめていたと思う。
じっさい、ぼくには「やめても、考え方は残るけん」という思いがどこかにありました。結局、「もうやめようぜ」の話し合いを経て残ったのは、自分たちの身の丈に合った展示会ばかりでした。夏に砂像が作れなくなった武政登さんは、1995年には鹿児島県加世田市の「砂の祭典」の砂像彫刻コンクールに参加して最優秀賞を取っています。

↑サンドクラフト全国大会(95年、鹿児島県加世田市)で砂像をつくる武政氏、この作品で見事優勝を果たした。
ところで、今後はどんな展開を考えていますか。
最近、考え方がストレートに伝わるような小さな事業があってもいいなと思うようになりました。それも生活に密着した、エコツーリズムのように地元の飲食店や農家と一緒にやるようなものです。
逆にというとストレートに伝わらないもどかしさがあるのですね。
たとえばTシャツアート展でいうと、応募した作品は波打ち際に打った杭にロープを張ってそこから吊るしていますから、杭ごと海に流されてしまうことがときどきあるんです。そんなとき、ぼくたちは海を漂うTシャツも作品に見えてしまいます。だけど出品者から見たら、それは単なる事故なんです(笑)。
そこのところはむずかしいですね。単にプリントしたTシャツが欲しくて応募する人だっているわけですし。

↑砂浜美術館での作品展示は常に天気との戦いでもある。悪天候ともなればTシャツが流されることも・・・
4キロの砂浜やクジラが棲める海を、
もしも人工的につくろうとしたら国家予算を投じても
できないかもしれない。
環境という視点から考えると、Tシャツアート展は入野の浜の歴史や自然に直接的な関心を呼び起こすものではありません。できればそこまで踏み込みたいのですが。
環境のことを外側に出していくとなると、町が内側で抱える問題まで情報発信していくことなります。
そこまでできると面白いですね。というのは、砂浜美術館の考え方は、たぶん、人間が生きていく上で大切なことをいっているのだと思うのです。じっさい、ものの見方が変わると大方町はすごい町なんだと思えてきます。考えてみれば、ドーム球場はないけれど、長さ4キロメートルの砂浜はあるし、沖にはクジラも泳いでいる。ついついドーム球場のほうに魅力を感じてしまうけれど、でも4キロの砂浜やクジラが棲める海を、もしも人工的につくろうとしたら国家予算を投じてもできないかもしれない。
そうしたことを、砂浜美術館の、同じものでも見方を変えると別の姿が見えてくるというアイディアを使っていかにお説教くさくなく外に向かって情報発信していけるかですね
【『砂浜美術館ノート』(1997年発行・非売品)より】
→「哲学の浜辺」第3部をちょっと解説:考え方は伝わるか
→「哲学の浜辺」第2部をちょっと解説:入野の浜と子どもたち
もっと読みたい方へ
砂浜美術館ノートⅡ
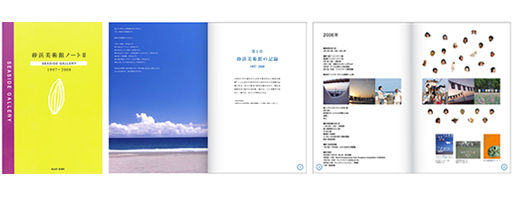
立ち上げに携わったスタッフとメンバーも入れ替わり、地域内外とさまざまな人が関わりながら活動を継続してきた砂浜美術館。そんな人びとのインタビューやエピソードを交えながら、1997年から2008年までの10年間の活動記録を掲載しています。
ながい旅でした。
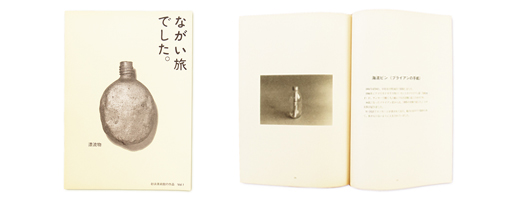
1994年4月18日に発行された漂流物についての冊子です。当時の砂浜美術館学芸員(自称)の想いとセンスがきいた解説は、20年近くが過ぎた今日でも色あせることなく、人の心に響いてきます。
ご興味のある方はコチラへ